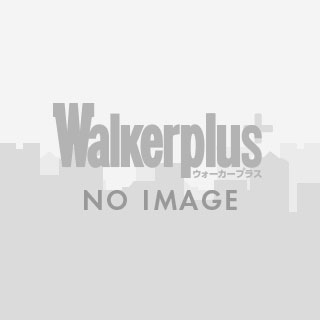【北鎌倉】禅文化に触れながら、仲間のつながりを深めよう
Sponsored by Airbnb Japan
東京ウォーカー(全国版)
2021年11月22日(月)~26日(金)に「鎌倉ワーケーションWEEK2021 Vol.1」というキャンペーンが開催される。民泊サービスで知られる「Airbnb(エアビーアンドビー、通称エアビ ー)」協力のもと、鎌倉のコワーキングスペースと連携したイベントだ。
ワーケーションとは「働く(Work)」と「休暇(Vacation)」を組み合わせた言葉で、ゆったりと旅先で仕事とバケーションを両立させながら楽しむ、という働き方のひとつ。
都心からも近く、自然豊かな鎌倉は、ワーケーションにぴったりの場所。今回は、鎌倉の文化に触れられるおすすめスポットのなかでも、禅寺の名刹が多い北鎌倉周辺で禅の心を学ぶスポットにフィーチャーする。

北鎌倉駅周辺は、時の権力者であり禅宗を保護した北条氏の所領で禅寺が残っている地域。鎌倉街道沿いや、徒歩数分圏内にたくさんの寺院が点在する。喧騒から外れた静かな街で、無心になる体験をしよう。ともに同じ体験をすれば、チームやグループの絆も深まり、より良いチームを作れそうだ。「禅」が世界に広く受け入れられている今だからこそ、この文化を学んでいこう。
1:広大な敷地に塔頭が立ち並ぶ「円覚寺」
北鎌倉といえば、季節ごとに見せるさまざまな表情が魅力のエリア。秋の紅葉はもちろん、春はサクラ、夏は深緑、と境内の美しい景色もまた見どころ。鎌倉を代表する寺院「円覚寺」は、境内の自然に癒やされつつも、禅寺の厳粛な空気に包まれている。
1282(弘安5)年、蒙古襲来による敵味方両軍の戦没者を弔うために北条時宗が創建。禅僧・無学祖元(仏光国師)が開山し、禅宗道場として発展した。
JR北鎌倉駅の線路沿いにある総門をくぐって境内へ。伏見上皇の勅筆「円覚興聖禅寺」の額が掲げられた山門をこえ、見えてくるのが仏殿。

禅宗様式である七堂伽藍の中心に位置する仏殿には、本尊である宝冠釈迦如来坐像(ほうかんしゃかにょらいざぞう)のほか、梵天、帝釈天が安置されている。前田青邨(せいそん)が監修し、守屋多々志(もりやただし)が描いた天井絵「白龍の図」も圧巻だ。


禅寺として毎朝、6:00〜「暁天坐禅会」を開催(グループでの参加は不可)しているが、終了後の散策はできない。8:00以降改めて拝観入場する必要があるため、参拝する場合は注意しよう。参加費は志納。

美しい庭園を持つ「方丈」にも注目。「方丈」とは本来、住職の居住する建物のこと。法要、坐禅会や説教会や秋の宝物風入など、現在の円覚寺では幅広く使われている。庭園は美しく、縁側から眺めることができるので、ぜひ拝観してみよう。方丈前には、無学祖元により植えられたと伝わる市指定天然記念物のビャクシンの木もある。

幾度も災害にあいながらも、その度に再建されてきた円覚寺。現在も禅寺として役目を果たしているのは、鎌倉の人たちに大切にされてきた証なのだ。
広大な境内は他にも見どころがたくさんあり、夏目漱石が「門」で書いた「帰源院」や、川端康成「千羽鶴」の舞台となった茶室など、数々の文豪が作品の舞台地にしたことでも有名(帰源院・茶室は通常見学不可)。参拝する際は、ゆっくり見て回りたい。
■円覚寺
住所:鎌倉市山ノ内409
電話:0467-22-0478
拝観時間: 8:00〜16:30(12〜2月は〜16:00)
拝観料金:大人500円ほか
休み:なし
駐車場:なし(周辺の駐車場を利用)
アクセス:JR北鎌倉駅より徒歩1分
公式サイト:
https://www.engakuji.or.jp/
2:日本料理から学ぶ和の心「鉢の木」でランチ
参拝で心がスッキリしたところで、次は季節の恵みを味わえる日本料理店ヘ。創業57年と伝統ある和食店「鉢の木」では、店内をワークスペースとしても利用できる(2021年11月現在)。こちらで午前の仕事をしながら、知恵と趣向が凝らされた和食に舌鼓を打とう。

地元の人のお食い初めから婚礼・弔いなど、人生の節目の日に利用されてきた「鉢の木」。「料理屋は、地域のよろず承り役です」と、代表の藤川譲治さん。緊急事態宣言が明けた今では「従来に増して、交流の場としてもお使い頂いています」とのこと。また、鎌倉を楽しむ観光客には、鎌倉の名所としても注目されている。

せせらぎが流れ四季が映し出された庭、大勢を迎えることができる大広間も持つゆとりある新館。ここで日本文化の真髄を堪能しよう。見た目も美しく食べ応えもある和食は、世界的にも注目されているジャンルの一つ。本格的な料理を、少し贅沢なランチで味わいたい。

季節により内容は異なるが「松花堂会席 松風」(5000円、税・サービス料別)は、先付、口取、炊合、胡麻豆腐、お造り、揚物など全8品。奥深い和食の世界を楽しもう。昼時は季節の会席ランチ(焼き魚膳2750円ほか)など、リーズナブルに味わえるメニューも。

ここでしか味わえない鎌倉時代の文化に触れられる日本食も特徴で面白い。「鎌倉武家祝い膳(時代食)」(8000円、税・サービス料別)は、食文化の基礎が築かれた鎌倉時代の食文化を再現された献立で、醤油の起源「醤(ひしお)」を使うなどしながら、食材本来の味を引き出している。8名以上のグループ予約で味わえる。
四季折々の素材を厳選し、独自の工夫で料理に仕上げる。華美な装飾はないが、禅の里にふさわしく、茶の湯における美意識を体験するのにも適した場と言える。
■鉢の木 新館
住所:鎌倉市山ノ内350
電話:0467-23-3723
営業時間:11:30〜13:30(LO)、17:00〜19:00(夜は完全予約制)
休み:不定
席数:新館124席※禁煙
駐車場:12台(無料)
アクセス:JR北鎌倉駅より徒歩5分
公式サイト:
http://www.hachinoki.co.jp/
3:浄智寺の奥に潜む 「たからの庭」で癒やされよう!
浄智寺谷戸にある、シェアアトリエハウス「たからの庭」。自然観察やヨガなどのワークショップや、カフェ、ギャラリーなどのイベントがそれぞれのクリエーターによって行われている。こちらで、知られざる鎌倉を発見しよう。

2009(平成21)年にシェアアトリエハウスとしてリニューアルオープン。元々、鎌倉時代から浄智寺の境内の一部でもあった場所で、現在も浄智寺の住職がオーナーを務める茶室「宝庵」も管理しているほど、浄智寺とはゆかりのある施設だ。

こちらでは常に「たからの窯の陶芸体験」ができる。日常使いの器を作る「葉っぱの器づくり」(3400円〜/各回定員8名/所用時間90分)、自由な形を作れる「手びねり体験」(5000円〜/各回定員8名/所用時間120分)、初心者もOKの「電動ロクロ体験」(5500円〜/各回定4名/所用時間90分)などのコースがある。陶芸体験(毎日開催)の申し込みはメール(taiken@tougei.email)にて。


観光の途中でも気軽に立ち寄ることができるところも魅力。陶芸体験はwebや電話で申し込みが可能(予約は3日前まで。空きがあれば、当日でも受付可能)。静かな中で何かに集中し、無心になる。これは「禅」の心とも通じるものがあるかもしれない。座禅とはまた違う、無になる体験を味わおう。
そのほか、「たからの庭」では古民家を維持し、それを活かした活動が行われているので、気軽に立ち寄ってみよう。
■たからの庭
住所:鎌倉市山ノ内1418
電話:0467-25-5742
営業時間:体験、開催イベントによる
休み:不定
※カフェを併設する「たからの庭ギャラリー」は金土日オープン。それ以外の曜日は各ワークショップの事前予約が必要。開催プログラムはHPのカレンダー参照。陶芸体験は毎日開催(要予約)
駐車場:なし
アクセス:JR北鎌倉駅より徒歩10分
公式サイト:
https://takarano-niwa.com/
4:静寂を感じる禅寺「浄智寺」
さて、「たからの庭」で集中する時間を過ごしたら、古都の風情が漂う「浄智寺」へ。
北条時頼の三男・宗政の菩提を弔うため、1281年頃(鎌倉中期)に創建された禅宗寺院。室町時代までは広大な境内を持ち、大いに栄えた寺院だが、現在は一部の建物を残すのみで静かに鎮座している。境内は、たくさんの木々に囲まれていて素朴ながら趣きを感じる。


御本尊の『阿弥陀・釈迦・弥勒』は室町期作で、それぞれ『過去・現在・ 未来』を表す木造三世仏と言われており、鎌倉仏の特徴をよく表している。県指定の重要文化財でもある、心願成就の仏様だ。

本堂の「曇華殿(どんげでん)」とは、「三千年に一度だけ咲く伝説の優曇華(うどんげ)の花」に由来しているそう。3体の神様にお参りできることは、そのくらい有り難いことであるという意味。
境内には、大正13年に建てられた茅葺の「書院」や、鎌倉七福神のひとつである「布袋尊」、当時の僧侶が使ったであろう「やぐら」、鎌倉十井(かまくらじっせい)の一つに数えられる「甘露ノ井」などもある。

こじんまりしている境内ながら、趣のある風景が楽しめる「浄智寺」。かつての景色に想いを馳せながら参拝するのも、充実した時間を過ごせそう。また、境内は国の史跡に指定されており、境内の横から源氏山ハイキングコースに繋がっている。初心者向けの低山なので、そちらまで足を伸ばすのもおすすめだ。
■浄智寺
住所:鎌倉市山ノ内1402
電話:0467-22-3943
営業時間:9:00~16:30
拝観料:200円
休み:なし
駐車場:15台(無料)
アクセス:JR北鎌倉駅より徒歩8分
公式サイト:
https://jochiji.com/
もっと楽しむなら!建長寺発祥のけんちん汁を味わえる「点心庵」
現代でも馴染みのあるけんちん汁。実は「建長寺」を開山した蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)が作った「建長汁(けんちょうじる)」がなまって呼ばれるようになったと言われる精進料理である。「点心庵」では、そんなけんちん汁を建長寺の門前で味わえる。

食材は主に鎌倉産のものを使用。建長寺に直接調理法を指導されているという、建長寺公認の「伝承 けんちん汁」(990円、小鉢・塩むすび2個のセット)。派手な見た目ではないが、ほんのり優しく「日本の食事の基本を思い出す」と人気で、北鎌倉の名物料理にもなっている。ニンジン、ゴボウ、里芋、大根、豆腐、レンコンなどの野菜がどっさり入っていて、寒くなってきた時期にはぴったりのメニューだ。

メニューが豊富でデザートも多数ある。おすすめは建長寺で採蜜した鎌倉はちみつを使ったのがポイントの「鎌倉はちみつプリン」(710円)。無添加で非加熱の鎌倉産はちみつ入りで、昔懐かしい味わい。

料理のうつわも、陶器は北大路魯山人の窯を継ぐ河村喜史氏のものを、漆器は鎌倉彫作家・三橋鎌幽氏の作品を使用。また、店内にはギャラリーを併設し、鎌倉の仏師・奥西希生の作品も展示している。実物を見たり、実際に使うことで、より深く知るきっかけにもなる。

「鎌倉に、少しだけ触れて頂く」がコンセプトの同店。至る所に、鎌倉を感じる要素が散りばめられているが、「坐禅堂」もその一つ。円窓から覗く手入れされた庭を眺めて、一息つこう。坐禅の手引きに沿っての坐禅体験(要問い合わせ)もできる。見学は自由なので、訪れた際はぜひ刮目しよう。
吉田正道老大師が名付けた店名の「点心」とは、禅語の「空腹(すきばら)に小食を点ずる」「簡単な食事」に由来しているとのこと。また、心に点をつけることから「心に触れるのもの」という説もある。日本の禅宗の草分けでもある建長寺の「けんちん汁」という文化。点心庵で味わうことで、禅の心に気軽に触れることができるというのもまた、貴重な経験だ。
■点心庵
住所:鎌倉市山ノ内7
電話:0467-55-9350
営業時間:11:00〜16:00(LO15:00)
休み:月曜(祝日の場合は翌日)
席数:40席※禁煙
駐車場:なし
アクセス:JR北鎌倉駅より徒歩14分
公式サイト:
http://tenshin-an.com/
鎌倉で宿泊するなら!
落ち着いた鎌倉で無心になる1日を…そんな気分の時は、宿泊施設を予約、掲載できるサイト・エアビーで宿泊場所を探そう。温熱療法のリラクゼーションサロン併設の「
stay&relaxation
」は築100年の古民家。居間の壁と天井は和紙を使った居心地の良い空間が、チームやグループで宿泊するのにもうってつけ!より繋がりが深まりそう。

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※新型コロナウイルス(COVID-19)感染症拡大防止にご配慮のうえおでかけください。マスク着用、3密(密閉、密集、密接)回避、ソーシャルディスタンスの確保、咳エチケットの遵守を心がけましょう。
この記事の画像一覧(全23枚)
キーワード
テーマWalker
テーマ別特集をチェック